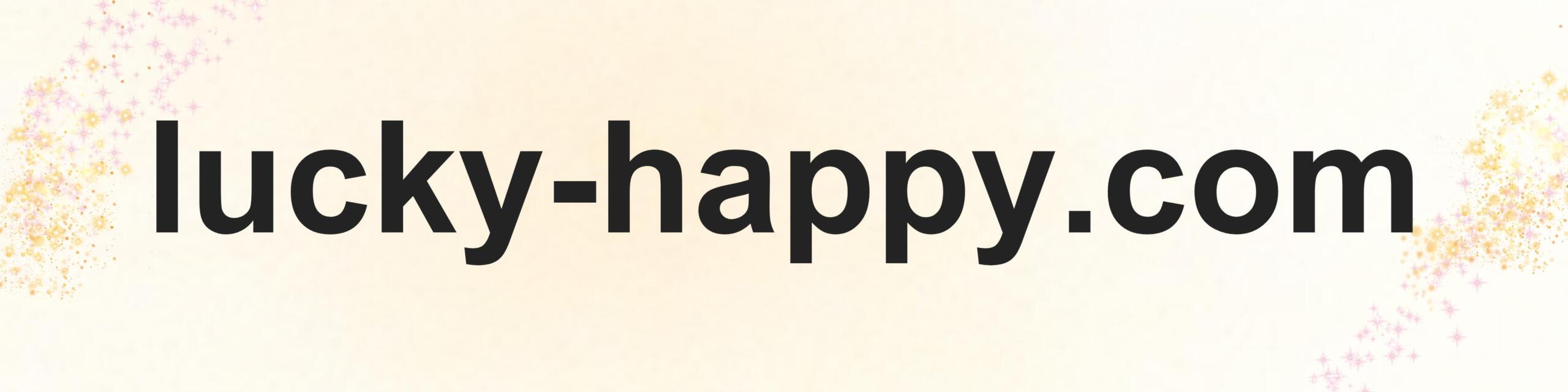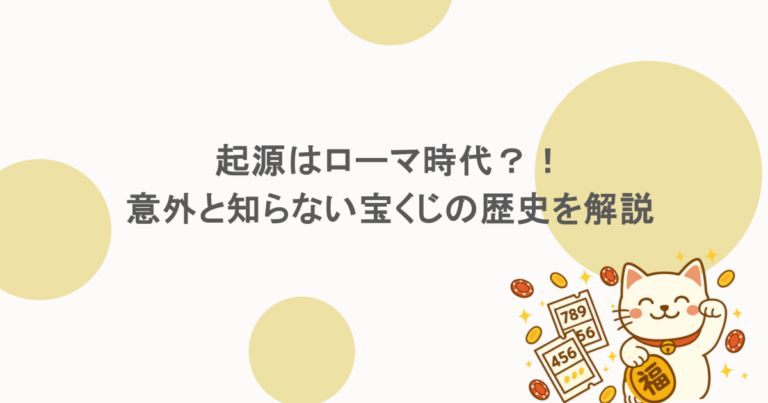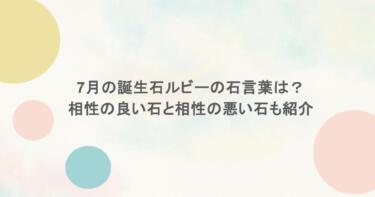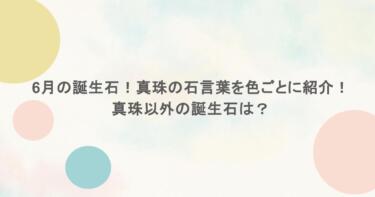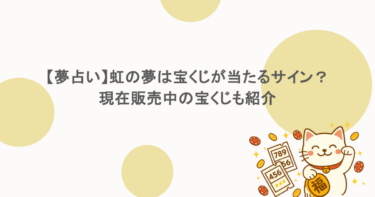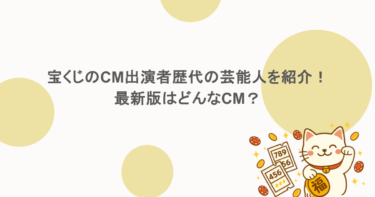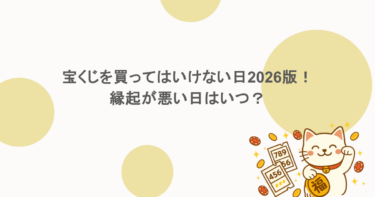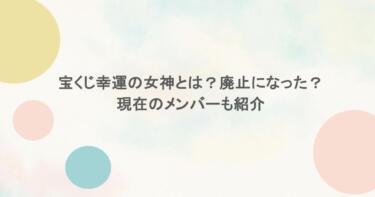一攫千金を夢見て購入する宝くじ。日本では、年に5回ものジャンボくじが発行され、ロトの種類もかなり増えています。宝くじは、古くから人々に親しまれてきていますが、そんな宝くじはいつから始まり、現代の宝くじへと発展したのでしょうか?今回は、あまり知られていない宝くじの歴史について、調査していきます。
宝くじの起源は?世界の宝くじの歴史
宝くじはの歴史は古く、紀元前から官職の決定や貴重品の配分に使用され、世界の観光名所の多くで貢献してきたと言われています。世界での宝くじの歴史を振り返ってみましょう。
古代の宝くじの歴史は、紀元前!
世界最古の宝くじは、中国での「木札によるくじ」と言われています。今から2200年以上前に、万里の長城の建設費の一部をくじの収益で賄った記録が残っているそうです。これが、宝くじの原型では?と言われています。
また、紀元前100年頃には、古代ローマで貴族たちの娯楽としてのくじ引きが行われており、公共事業の資金調達のために商品付きのくじ引きが実施されたようです。
15世紀ごろに中世ヨーロッパで宝くじが登場!
1400年代に、イタリアのミラノでくじの記録が残っています。またオランダでは、宝くじが発行され、公共事業や貧困層の支援に使われたそうです。
1500年代になると、国の財政を支えるためにイギリスで初の公式宝くじが開催され、商品は現金の他、工芸品や金銀なども含まれていたそうです。
18世紀ごろにアメリカで宝くじを利用!
アメリカでは、公共事業やハーバード大学などの教育機関の建設費用として、宝くじが利用されました。
しかし不正や賭博といった問題が発生し、一時禁止となった事もあったようです。その後、20世紀には合法的な国営宝くじが復活しています。
日本の宝くじはいつ始まったの?
では、日本の宝くじの歴史はいつ頃から始まったのでしょうか?ここからは日本の宝くじの歴史について、ご紹介します。
日本の宝くじの起源は「富くじ」
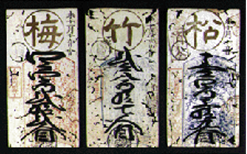
【以下出典:宝くじ公式サイト】
日本では、1624年(1575年説もあり)頃に、摂津国(現在の大阪)の箕面山瀧安寺で行われたことが始まりとされています。正月の7日間に参詣し自分の名前を書いて木札を唐びつの中に入れ、7日に3人の当せん者をキリでついて選び、福運のお守りを授けました。
その後、次第に金銭と結びついていき、町にはんらんした為に、幕府は禁止令を出した事もあります。
ただし、寺社だけは、修繕費用調達のために富くじの発行を許可し、「天下御免の富くじ・御免富」と呼ばれていました。
天保13年には、天保の改革により御免富も禁止され、その後103年間の長きにわたり富くじの発行はされませんでした。
「宝くじ」として発売
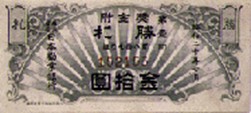
昭和20年に、軍事費の調達のために1枚10円で1等10万円が当たる富くじ「勝札」が発行されました。しかし、抽選日を待たずして終戦となったため、「負札」と呼ばれてしまいました。同年10月には、戦後のインフレもあり、「宝くじ」の名で政府第1回宝籤が登場しました。また、戦災で荒廃した地方自治体の復興資金調達の為に、各都道府県でも独自で宝くじを販売できることとなり、昭和21年に第1号となる「福井県復興宝籤(ふくふく籤)」が発行されます。昭和29年に政府宝くじは廃止となり、地方自治体が発売した「自治宝くじ」だけが残る事となりました。
現在に繋がる原型となる自治宝くじが誕生
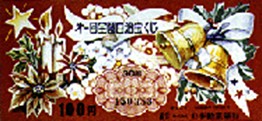
昭和29年には「全国自治宝くじ」が誕生します。経済復興につれて各地域の自治宝くじ連合の活動も加速し、昭和34年までに現在のブロック(東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじ)の原型ができました。
オリンピックと賞金の高額化!

昭和30年代後半は、日本はオリンピックブームとなり、東京オリンピックまでの5年間は、オリンピックマークを入れて宝くじが発売されました。
高度成長期へと入った事で宝くじの規模も拡大し、賞金は昭和40年には700万円、41年には800万円、43年には1000万円となっていきます。
この頃になると、宝くじ売り場には大勢のファンが訪れ、行列になる事もありました。
「宝くじの日」と「地域医療等振興自治宝くじ」の登場
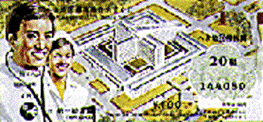
万博や、札幌冬季オリンピック、沖縄海洋博などに協賛する宝くじの発売などもあり、ますます宝くじ人気が高まっていきました。賞金が高額化した事もあり、混雑解消のために予約制やユニット制を導入し、さらに発売額が大きくなりました。昭和42年から「9月2日」は「宝くじの日」として、当せん金の時効防止を呼び掛けるようになりました。
また、昭和49年には自治医科大学の整備資金調達のために「地域医療等振興自治宝くじ」の販売も開始され、長寿社会のための事業などの財源を助成しています。
ジャンボ宝くじの登場!

年3回発売された予約制の宝くじが、昭和54年には「サマージャンボ宝くじ」として発売され、以降「ジャンボ宝くじ」と呼ばれるようになりました。昭和55年には「ドリームジャンボ宝くじ」で、1等賞金3000万円となり、ドリーム、サマー、年末の3大ジャンボが人気となります。賞金も高額化し、昭和60年には1等5000万円、平成元年には1等6000万円前後賞あわせて1億円となっていきます。その後グリーンジャンボ(現バレンタインジャンボ)とオータムジャンボ(現ハロウィンジャンボ)が登場し、現在では5大ジャンボとして親しまれています。
数字選択式宝くじの登場と大型化する賞金体系

宝くじファンのニーズに合わせたインスタントくじ、イベント宝くじ、欧米で主流となっていた数字選択式宝くじも登場していきます。
平成6年には「ナンバーズ」、平成11年には「ミニロト」、平成12年には「ロト6」、平成25年には「ロト7」、平成29年には「ビンゴ5」が登場しました。
また、最高賞金もどんどん高額となっていき、平成27年には年末ジャンボ宝くじで1等7億円、前後賞合わせて10億円となり、10億を突破しています。その後平成29年にはロト7の最高賞金額が10億円となり、2025年2月からの最高賞金額は12億円となっています。
まとめ
今回は、あまり知られていない宝くじの歴史について、ご紹介いたしました。現在もジャンボ宝くじの発売初日などは、ずらっと並んだ光景を目にすることがあると思います。当たり前のように宝くじを購入していましたが、調べてみると意外な歴史があるものです。どんどん賞金も高額化する宝くじ。これからどんな風に発展していくのかを楽しみにしながら、宝くじを購入して大きな夢を叶えたいですね。