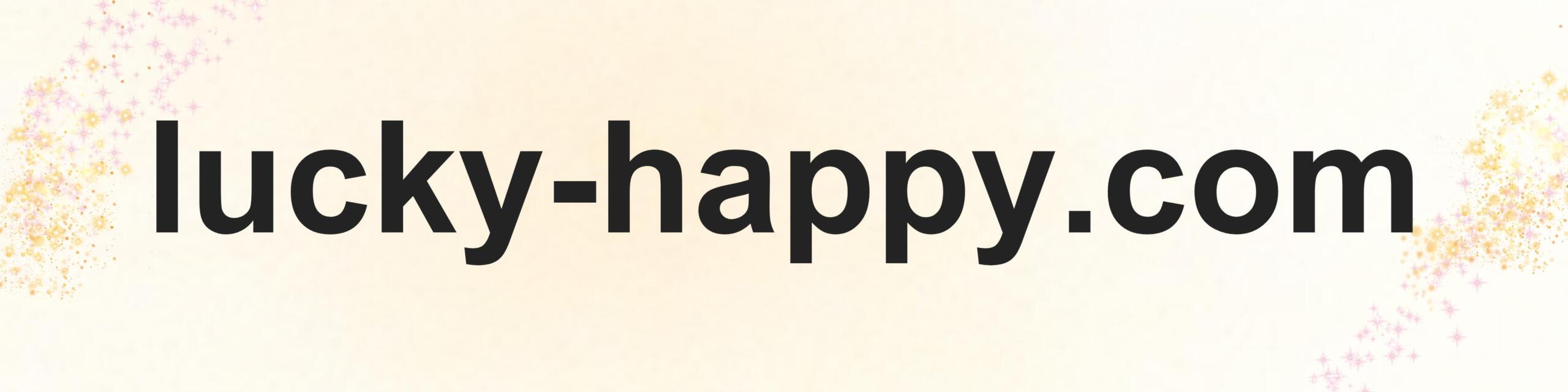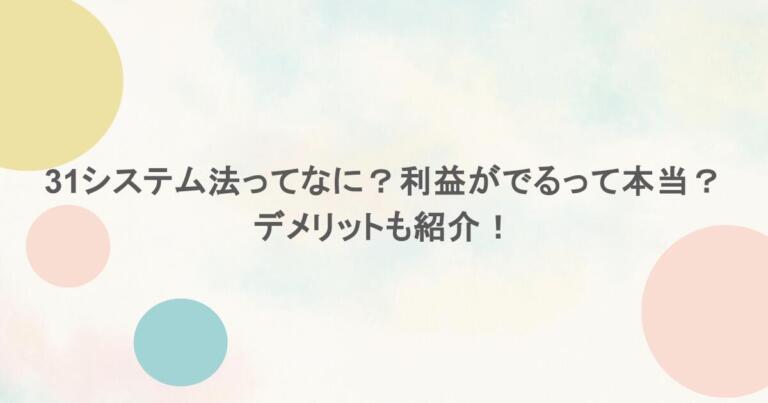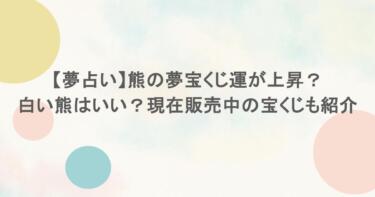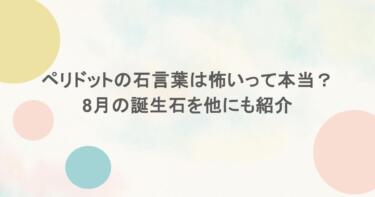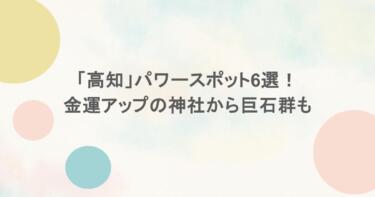ライブカジノやブックメーカーでの賭け方にはさまざまな攻略法がありますが、なかでも「勝率を上げたい」と考える人の間で注目されているのが「31システム法」です。
独自の賭け方ルールを用いることで、連勝による利益確保をめざす資金管理法のひとつで、比較的リスクを抑えながら利益を狙える手法として注目されています。特に連勝時のリターンが大きくなることから、多くのプレイヤーが取り入れています!
今回は、31システム法の仕組みや使い方、実際に利益が出るのかといった疑問、さらにメリット・デメリットまで詳しく解説していきます!オンラインカジノ おすすめランキングをチェックする前にぜひ最後まで読んでくださいね。
31システム法とは?
まずは、31システム法の基本的な考え方について確認しましょう。他のベッティングシステムと同様、連勝と連敗のバランスを活かし、トータルでの利益を目指すロジックが特徴です。
31システム法は、あらかじめ定められたベット単位の合計「31」をベースに賭け金を調整していく攻略法です。具体的には、「1,1,1,2,2,4,4,8,8」のような配列を使い、勝った場合は数字を消し、負けたら合計して次回ベットします。
最終的にすべての数字を消せれば、一定の利益が得られる仕組みです。
極端な連敗には弱いものの、2勝1敗程度のペースでも利益が見込めるため、初心者でも扱いやすいのが魅力です。
31システム法の使い方
では実際に、どのように31システム法を使っていくのか、その流れを見ていきましょう。ここではベット配列の管理方法や実践の手順を解説します。
ベット配列の準備とルール
31システム法では、「1,1,1,2,2,4,4,8,8」という数字の並びをあらかじめメモしておきます。各数字はベット単位を表し、合計が31になるように設計されています。プレイヤーは、リストの最初と最後の数字を足した額を次のベット額として使用します。勝てばその2つの数字を消し、負ければその合計額をリストの末尾に追加します。この繰り返しによって、勝ちが続けばリストが短くなり、最終的に「全部消す=利益確定」が目標となります。
実際のプレイ例
たとえばリストが「1,1,1,2,2,4,4,8,8」の状態で、最初のベット額は「1+8=9」となります。これに勝利すれば「1」と「8」を削除し、次は「1+8=9(残った別の8)」でベット。連勝を重ねるごとに数字は減っていき、すべて消えれば勝ち。逆に負けた場合は「9」を末尾に追加して、「1,1,1,2,2,4,4,8,8,9」となり、次の賭け金は「1+9=10」に変化します。
31システム法は利益がでるのか?
攻略法として使用される31システム法ですが、果たして本当に利益が出るのか気になる方も多いはずです。実際の期待値やリスクの観点からその可能性を解説すると、31システム法は、理論上2勝1敗のペースであれば利益が確定する設計になっています。ベット額の増加は緩やかで、急激な損失に繋がりにくいことから、資金管理をしやすいのが特徴です。ただし、長期的に見ればカジノ側の控除率(ハウスエッジ)があるため、勝ち続ける保証はありません。
短期的なセッションでコツコツと利益を狙いたい人に向いている攻略法といえるでしょう。
どんなメリット・デメリットがあるかも紹介
31システム法には、他のベッティングシステムにはない特徴があります。
ここではそのメリットとデメリットを具体的に整理し、自分に合った運用ができるかを見極めていきましょう。
メリット1:緩やかなベット上昇で安心
31システム法の魅力のひとつは、連敗時でも急激にベット額が増えないことです。
他のシステムのように倍々に増えるリスクが少ないため、資金をゆるやかに消費しながら長くプレイを楽しめます。
メリット2:明確な勝利条件がある
「全ての数字を消せば勝ち」というシンプルなルールのため、進捗が可視化しやすく、達成感も得やすいのもメリットと言えますよね。
初心者にも目標がわかりやすく、戦略性が理解しやすい構造です。
デメリット1:リストが長くなりがち
連敗が続くと、追加する数字によってリストがどんどん長くなり、管理が煩雑になることもあります。
どこでリセットすべきか、判断に迷う場面も出てくるでしょう。
デメリット2:大勝ちには不向き
31システム法はあくまで「小さく勝ち続ける」スタイルのため、短時間で大きく稼ぐ戦略には向いていません。
高額なリターンを狙いたい人には、別のシステムが合っているかもしれません。
まとめ
風水などで願掛けするのも一つの手かもしれませんが、オンカジ初心者にも扱いやすい31システム法を覚えておくとよりベットが楽しくなるでしょう。リスクを抑えつつ利益を狙える構造になっており、資金管理がしやすい点で多くのプレイヤーに支持されています。
ただしどんな攻略法でも万能ということはなく、長期プレイではハウスエッジの影響も受けるため、あくまで補助的な手法として活用するのがベストです。
自分のプレイスタイルや目標に合わせて、活用の可否を検討してみましょう。